足尾銅山観光(栃木県)坑道3

足尾銅山の魂
岩を掘る時に使う鑿岩機(削岩機)。
現在、この世界的シェアを誇る会社が、
足尾銅山開発で飛躍した
古河グループの一つ
「古河ロックドリル」です。
Wikipediaによると
「足尾銅山(明治10年に経営開始)で
使用された機械の
製造・修理部門が事業の発祥で、
ここから様々な開発機械を
開発・製造していき、今日に至る。
1914年(大正3年)には、
日本初(国産第一号)の削岩機
「手持ち式削岩機」を開発した。
現在では、世界100ヶ国へ輸出するなど
鉱山用機械の世界トップメーカーとして
事業を展開している。」
このように記されていています。
元々、
足尾銅山で使っていた
輸入品の鑿岩機が日本人の体型に合わず、
「何とかしなきゃ!」と
必要に迫られて独自に開発した結果、
その鑿岩機が、
多くの現場に出回ったのが始まりで、
その後、大型鑿岩機の開発などを経て、
現在のリニア中央新幹線のトンネル工事でも、
「古河ロックドリル」製品は、
多く使われているようです。
現代技術の粋を集めたリニア中央新幹線、
実は足尾銅山の魂が入っていたんですね!
昭和時代
坑内展示のフィナーレを飾るのは、
僕たちの生まれた昭和時代です。
現在36歳以下の人は、
平成以降の生まれですから、
昭和時代は、
かなり昔でもあるんですね(笑)
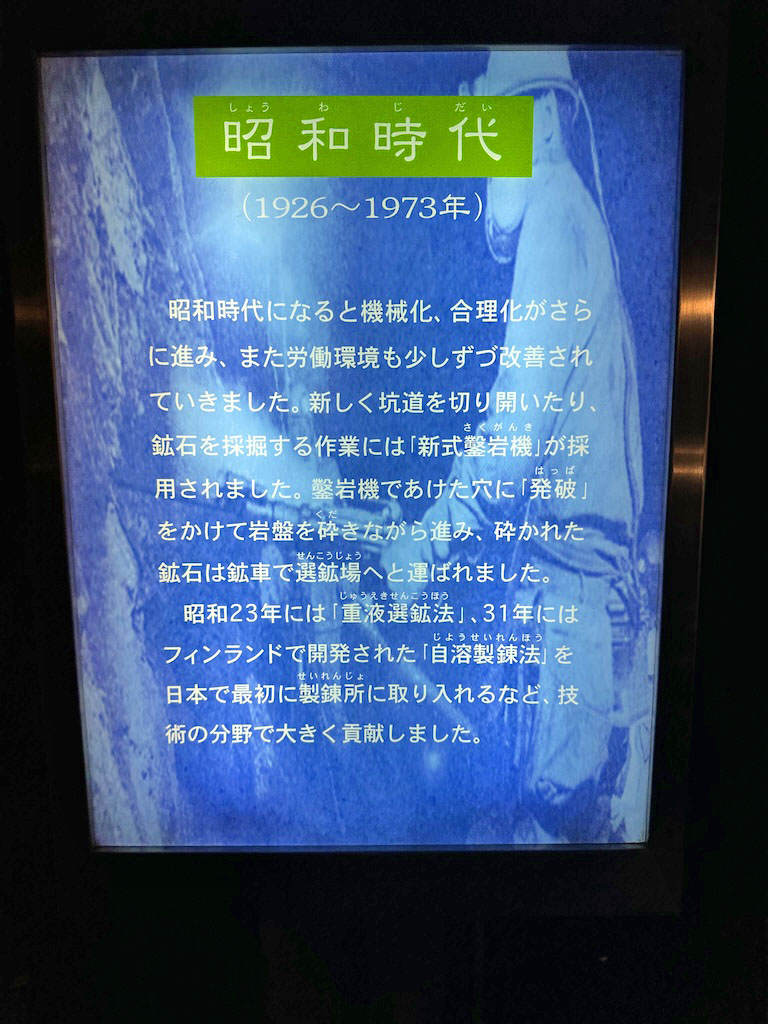
「昭和時代
(1926〜1973年)」
以下、案内です。
「昭和時代になると機械化、
合理化がさらに進み、
また労働環境も少しずつ
改善されていきました。
新しく坑道を切り開いたり、
鉱石を採掘する作業には
「新式鑿岩機」が採用されました。
鑿岩機であけた穴に「発破」をかけて
岩盤を砕きながら進み、
砕かれた鉱石は鉱車で選鉱場へと
運ばれました。
昭和23年には「重液選鉱法」、
31年にはフィンランドで開発された
「自溶製錬法」を
日本で最初に製錬所に取り入れるなど、
技術の分野で大きく貢献しました。」
ここに書かれている「新式鑿岩機」、
これが古河グループ独自開発のもの
かも知れませんね!

鑿岩機での作業風景。

弁当食べてる風景。

お題は「休憩する坑夫」です。

弁当食って、
めっちゃ幸せそう!(笑)

顔の汚れもリアルで完璧!
付け入る隙がありません・・
毎度言ってきましたが、
この展示を作った人の「心意気」、
ダイレクトに感じまくっています!

次は開運洞へ。

もうすぐ到着。

参拝。

奥の御神体?
鳥居の向こうには石の水槽があり、
水が溢れ出ています。
御神徳などの記載はありませんが、
やはり鉱山の神様といえば、
石見銀山にも鎮座していた、
「金山彦命」、
この神様の関連かと推察します。
(勝手な想像です)

さらに奥へ・・

誰かいますね!

保安員の方かな?

いや〜これもリアル!
本物の人と言っても
不思議じゃない感じです(笑)

もうすぐ坑道出口。
とにかく感動した
坑内展示でした!







