鑁阿寺(足利氏館)経堂

伝承と検証
巨木(御神木)などには、
「千年前、○○の御手植え」など、
樹齢を遥かに超えているであろう
伝承が記されていたり、
建造物に関しても、
実際のものよりも古い時代の伝承が
記されている場合もありますが、
これらはあくまでも「伝承」なので、
何も問題はないでしょうが、
鑁阿寺の案内は、
これらとは一線を画するものでした。
案内の多くが、「伝承と検証」
この二つを併記してあるという
画期的なもので、
「案内文の理想系」とは
言い過ぎでしょうが、
とても心地良く観覧出来た
思い出が残っています。
大銀杏
本堂(大御堂)参拝後、
本堂向かって左手前の大銀杏へ。

参拝場所と石玉垣が設られ、
見るからに大切感満載です。

「天然記念物 大銀杏」
「開基足利義兼の御手植えと称しているが
鎌倉時代末期正和年間(1310年)の
当山の古地図には載っていない。
故三好学博士の鑑定によれば
樹齢約五百五十年といわれる。
江戸時代には既に大木となり
樹下に於いて大日如来のお堂を前にして
青年男女の見合いが行われ、
縁結びの御神木ともいわれている。
目通り周囲九米。高さ約三十米。
往古より避雷針の役目を果たし、
諸堂の災厄を守護した。
最近、樹勢とみに衰え
衆民の愛護を切に望む。
真言宗 大本山 鑁阿寺」
このように記され、
冒頭に書いた、
「伝承と検証」が成されていて
素晴らしい案内だと思います。
そして、
案内板手前の石ベンチに注目・・・
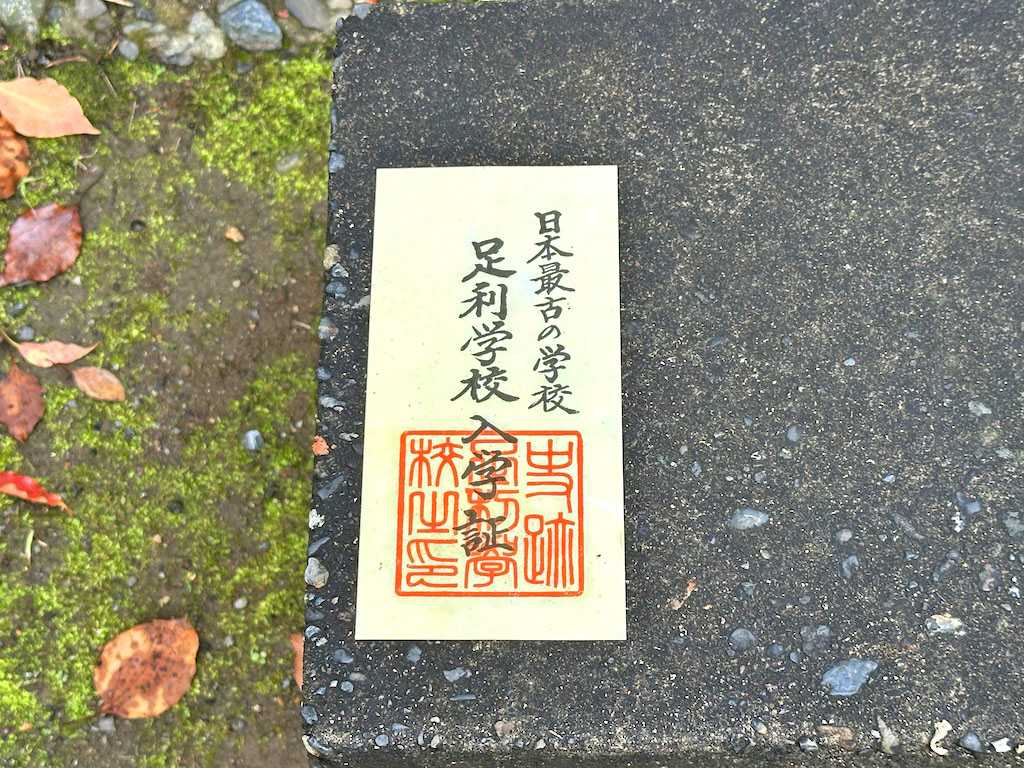
「日本最古の学校
足利学校 入学証」
昨日来られた旅行者のどなたかが、
ここに忘れて行ったのでしょう。
鑁阿寺のすぐ近くには、
教科書にも出てきた足利学校があり、
旅計画の最後の最後まで
何とか行けないかと模索はしたものの
時間の都合上、訪問を断念しました・・
そんな僕の気持ちに寄り添うかのような
「入学証」の出現に驚き、かつ、
大銀杏と鑁阿寺の霊験を感じたものです。
これを置き忘れた旅人さん、
「あなたは残念かも知れないが、
こんなに喜ばせて貰った者がいます。
本当にありがとう!」
この言葉を贈ります。

別角度から。

根っこの大きさを妻と比較。
多宝塔
大銀杏の横の道が、
多宝塔への参道です。

正面。

斜めから。
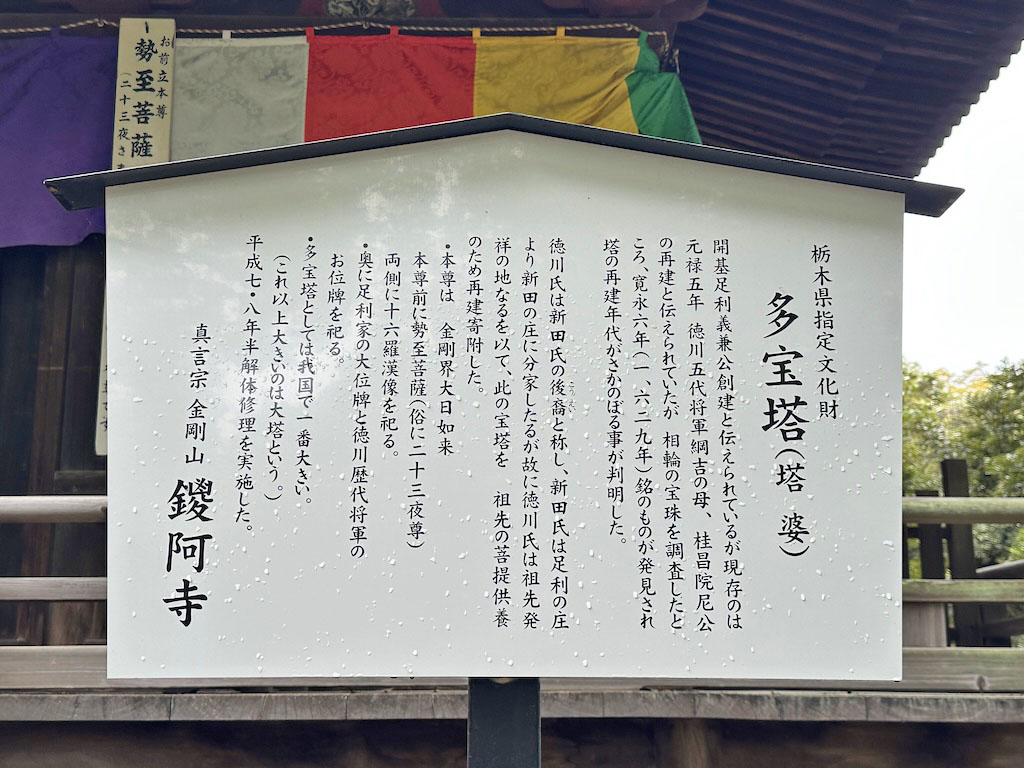
「栃木県指定文化財 多宝塔(塔婆)」
「開基足利義兼公創建と伝えられているが
現存のは元禄五年 徳川五代将軍綱吉の母、
桂昌院尼公の再建と伝えられていたが、
相輪の宝珠を調査したところ、
寛永六年(1629年)銘のものが発見され
塔の再建年代がさかのぼる事が判明した。
徳川氏は新田氏の後裔と称し、
新田氏は足利の庄より
新田の庄に分家したるが故に
徳川氏は祖先発祥の地なるを以て、
此の宝塔を
祖先の菩提供養のため再建寄附した。
・本尊は 金剛界大日如来
本尊前に勢至菩薩(俗に二十三夜尊)
両側に十六羅漢像を祀る。
・奥に足利家の大位牌と
徳川歴代将軍のお位牌を祀る。
・多宝塔としては我国で一番大きい。
(これ以上大きいのは大塔という。)
平成七・八年半解体修理を実施した。
真言宗 金剛山 鑁阿寺」
このように記され、
こちらは詳しい調査をしたら、
年代が遡ったという例です。
寛永六年(1629年)と言えば、
三代将軍徳川家光の時代、
徳川家祖先の菩提供養のための建立なので、
多宝塔建立は家光さんの差配だった
かも知れませんね。

勢至菩薩(二十三夜尊)の石塔。
ご本尊よりも主役になっています(笑)
中御堂(不動堂)
本堂横の中御堂へ。

エントランス。

中御堂正面。

「中御堂(不動堂)」
「寺伝では開基足利義兼公の創建とあるが、
文禄元年(1592年)
生実御所国朝の再修になる。
御本尊不動明王は従古千葉県成田山より
勧請せるもので興教大師の作といわれ
霊験あらたかな不動明王である。
本堂が明治四十一年国宝に指定される迄は
不動堂と廊下でつながっていて
四度加行の護摩法の道場として
使用した堂宇である。
昭和四十四年信徒の浄財により
半解体修理を実施した。
商売繁盛を祈念する堂であると同時に
酉年守本尊なり。
堂の右側に古井戸の跡あり
八百年前足利氏が居住した時に
使用したといわれる。
真言宗 大本山 鑁阿寺」
このように記され、
やはり伝承と検証で、
濃い内容になっています。
ここで書かれた興教大師は、
九州は佐賀県鹿島市の出身で、
高野山中興の祖と言われる方で、
根来寺を創建した人です。
根来寺は豊臣秀吉から徹底的に
攻撃されて伽藍の多くは焼失、
その後、
紀州徳川家が復興し今に至っています。
4年前、高野山でこんな経緯を知った時、
根来寺へ行きたい!
と思っていたのですが、
いつしか忘れていました(汗)
ここで興教大師の名前に触れたのは、
「ボチボチ根来寺へおいでなさい!」
と言う根来寺さんからの
熱〜いメッセージなのかも知れません(笑)

参拝。
経堂
次に経堂へ。

参拝。
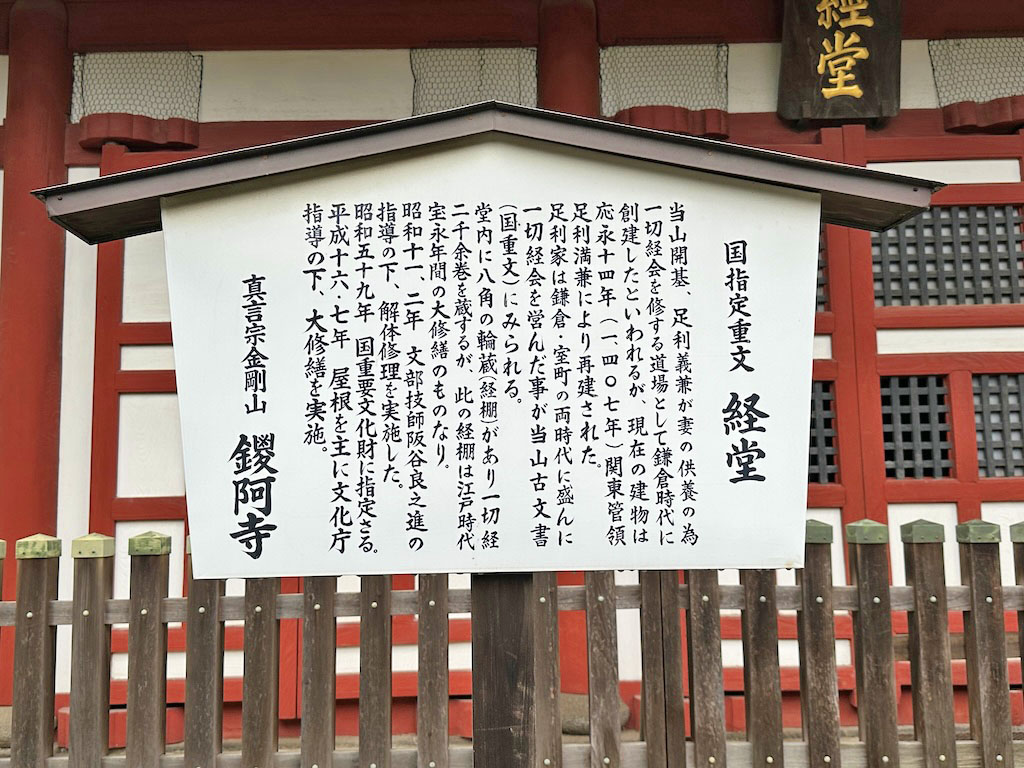
「国指定重要文化財 経堂」
「当山開基、足利義兼が妻の供養の為
一切経会を修する同条として
鎌倉時代に創建したといわれるが、
現在の建物は応永十四年(1407)
関東管領足利満兼により再建された。
足利家は鎌倉・室町の両時代に
盛んに一切経会を営んだ事が
当山古文書(国重文)にみられる。
堂内に八角の輪蔵(経棚)があり
一切経二千余巻を蔵するが、
此の経棚は江戸時代宝永年間の
大修繕のものなり。
昭和十一、二年
文部技術師 阪谷良之進の指導の下、
解体修理を実施した。
昭和五十九年 国重要文化財に指定さる。
平成十六・七年
屋根を主に文化庁指導の下、
大修繕を実施。
真言宗金剛山 鑁阿寺」
以上のように記されています。
「八角の輪蔵」というのは、
回転式の書架で、
これを一周回すだけで、
中に納められた経典を全部読んだのと
同じご利益があるというものです。
罪穢れが無かったことになる
神社での大祓や人形流しなどで、
いい意味での
日本人らしい考え方の象徴でしょう。

扁額。

斜めから撮影。
この後、「源氏の祖」を祀る
御霊屋へと向かいます。
(続く)







